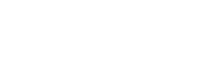『薔薇王の葬列』菅野文
-
「読み応え満点なこの作品。まだまだ認知度が低いことがネック。女性に限らず、男性にも一気読みをオススメ!」
「歴史は厳密には科学であって文学ではない。現在の時間で起こっていることのすべてが事実の積み重ねであるように、過去の時間で起こったこともすべてに事実があって、その積み重ねと繋がりによって歴史は作られて来た。時間を巻き戻して原初まで遡ってカメラで撮影していけるのなら、歴史の本には事実だけが書かれ、登場人物たちによる言動もすべて事実によって裏打ちされたものになる。それは面白いかどうかはともかく。いや、事実であっても面白い人はいる。現実に今のこの時間を生きる少なくない人たちの人生といったものが、とてつもなく面白い物語として見られ読まれ感じられている。事実は小説よりも奇なりというように、奇妙奇天烈な人生を歩んだ人たちの足跡を、圧倒的な物語として味わうことが出来ている。けれども、だから歴史から文学を廃してしまって良いということにはならない。過去に遡ってすべてを記録するカメラが存在しない以上、その時に起こったことを知るためには、残された書物であり、絵画であり、遺物であり、口承でありといったものを集め、そこから何が起こったのかを探り、想像し、類推して重ね合わせ、ひとつの時間を織り上げてくしかない。そこには必然として、物語を想像して飛躍させる文学の所作が必要となる。歴史としての、あるいは科学としての事実から逸れてしまったもの、かけ離れてしまったものも混じってくるかもしれない。ただの庶民が英雄に祭りあげられていたり、凡庸な君主が英明な支配者として讃えられているかもしれない。逆に、聡明な君主が悪逆非道の限りを尽くした暴君として誹られることも起こるだろう。だからといってそれは事実ではないと廃して何の意味がある? 必要なのは、歴史においてそういう人物が存在したこと、そして様々な物語を残して去って行ったことを想像する文学の言葉だ。例え事実からかけ離れていても、過去に存在し得ただろうそうした人物が、残し得たかもしれないさまざまな物語を求めることで、そこに真実味を感じさせる歴史のビジョンが浮かび上がる。それを受け取り、読むなり見るなり聞くなり味わうなりして僕達は、遠く過ぎ去った時間に思いを馳せ、今という時間に予定調和的な諦めの延長ではない、創造と冒険に溢れた時間を歴史上の事実として刻んでいく。ここに誕生した歴史上の人物たちを主役にし、歴史上の出来事を文学という形に変えて刻み続けた偉大なる劇作家の著作も混ぜて紡がれた菅野文による『薔薇王の葬列』(秋田書店)という漫画もまた、想像と飛躍にあふれた過去の時間を見せてくれる。リチャード三世という、ウィリアム・シェイクスピアの戯曲では残酷にして狡猾な君主とされた男を物語の中心に据え、その肉体にとてつもない秘密を持たせ、だからこそ育まれた鬱屈と渇望を言動に反映させながら、戦乱に明け暮れた中に育ったからこそ持ち得た知略も載せて、激動の薔薇戦争を乗り越えていく姿を描き出す。シェイクスピアに「ヘンリー六世」という史劇も書かせたほど、素材にあふれた時代だけあって後にリチャード三世となる少年リチャードが直面する事件はダイナミズムに溢れ、王位をめぐって対立する王族や貴族たちの権力に貪欲な様子も、繰り返される戦乱や企まれる謀略の中に描かれる。およそ事実として伝えられているそうした事件を味わいつつ、一方で特別な肉体を持って生まれてしまったリチャードの葛藤や懊悩に触れ、その心情に寄り添いながらリチャードが何を望み、何を求めて生きていたのかといったことを、想像の中に辿っていける。それは事実ではなかったかもしれない。だからといって虚構と切って捨てて良いものでもない。肉体に不具合があったと伝えられるリチャード三世が、父を奪われ兄を廃される中で戦い、勝ち得た王位をやがて奪われていく歴史上の出来事の裏側に、もしかしたらあったかもしれない要素として、含み置いて考えることを誰が咎め立てられよう。仮にそうだったからこそ、こうなったかもしれない歴史の帰結。その延長としての現在。そう思うことで関心の無かった過去がぐっと身近になってくる。そこからいまいちど、本当の事実とは何だったのかといった想像にも、思考を向かわせることができるのだ。積み重なっていく巻数の中でリチャードは、だんだんと変化していく己の肉体に戸惑い、時に嫌悪しながらもその肉体を使い危地を脱していく。漫画では絵によって特別なら肉体を持ってしまった人物像を、少年性というよりも中性的な雰囲気を持ったスタイルによって描き出す。実在の肉体に依らない漫画だからこその自在さが、そうした人物描写を化膿している。見ればどちらとも取れ、どちらにも取れない曖昧な存在が見え、だからこそそれを己と意識して苦悩するリチャードの姿が見えてくる。そこにはいったいどんな葛藤があるのだろうか。それとも次第に肉体の側へと靡いていく心情があったのだろうか。第5巻の終わりにかけてリチャードに浮かんだひとつの感情、あるいは恋情といったものに漂う変化する心情が、王位を目指す物としての立場と、変化を続ける肉体とのギャップの中でどういう方向に膨らんでいくのかが、今は知りたくてならない。事実としての歴史では、リチャードはいずれ王となってそしてボズワースの戦いに臨み戦死する。ヘンリー六世は王位に復帰した後に退位させられ、ロンドン塔で処刑され、ヘンリー六世の息子のエドワードも処刑される。リチャードの周囲に現れ関わりを持った者たちの、そうした事実が物語のなかでどう描かれ、それによってリチャードにどのような変化が起こるかも、これからの展開で興味が向かうところだ。そこまで描かれるのかも含めて、これからも紡がれていく物語に、物語としての事実に目を配っていこう。」